[ 赤毛の優男 長身の男 ]
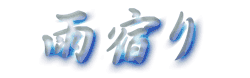
〜 赤毛の優男 〜
拙者にとって、それは突拍子もない存在。
晴れているはずなのに現れたり、
曇っているにもかかわらず、こちらの予想を容易く裏切り。
果ては、視界を遮るほどに自らの存在を主張する・・・
この日も、それは現れた。
左之助に誘われるがままに賭場へ出向いた、その帰り道に。
「おっ。何でェ、降ってきやがった」
傍らの彼の声に、拙者も思わず、空を仰ぐ。
・・・暗雲たれ込み、今にも落ちてきそうな気配。
落ちてくるものは雲ではなく、「雨」なのでござるが・・・
水の粒は、ポタリと拙者の十字傷を濡らした。
「こうしちゃ、いられねぇや。おい、剣心ッ」
やや呆然として仰いでいた拙者を、左之助の力強い腕が伸びてきた。振り払う以前に・・・いや、そうした気概などもとよりないのでござるが、そんなことを考える暇を与えられぬほど、左之助は強引に拙者の腕を掴んで走り出した。
目の前に翻る「惡」が、ほんのりと頼もしく見える・・・
「よっしゃ、とりあえずここで、雨宿りな」
ニッコリと微笑んで言った左之助が選んだ場所は、神社の境内も近い、樹々の生い茂った小道でござった。
傍らにどっしりと構えている樹を選び、左之助は拙者を引っ張って幹へと身を寄せた。
「雨にやられるたァ、ついてねぇなぁ・・・」
愚痴をこぼすような余韻に、拙者はつい、苦笑してしまった。
「あぁ・・・そうでござるな」
「ま、いいや。今日はかなり、儲けたしな。ありがとよ、剣心」
無理矢理連れ出されたあとに、このような笑顔を見せられてしまっては・・・このような、素直な礼を言われてしまってはもう、胸に支えていたはずの小言など失せてしまう。
常々、そうしてこの男の笑顔に、言わねばならぬ事をうち消されてきたように思う・・・
それらもすべて、左之助のなせる技なのやも知れぬ。
「よく・・・降るなァ・・・」
何かを堪えていたかのように、雨は一気に降り出していた。
現実から隔離してしまうかのように。
「・・・雨、か・・・」
拙者は一人呟き、顔を伏せた。
雨は・・・見たくなかったゆえに。
・・・雨など、嫌いだった。
「あなたは本当に、血の雨を降らすのですね」
と言った、かつての愛しい人を思い出させるから。
・・・雨など、疎ましかった。
ただただ、闇雲に世の中を・・・
この世のすべてを、遮ろうとするから。
「雨など・・・」
その時、拙者の背中を悪寒が走り抜けた。
時節は水無月、梅雨の時期。
雨が降るのは当然でござるが、悪寒が走るのは道理に適わぬ。
どうやら・・・この蒸し暑さにも拘わらず、雨で身体が冷えかけているようだった。
拙者はついと、左の袖を揺らし、懐手にしようとした。
「待てよ、剣心」
・・・不思議なことと、思うのでござるが。
時として、左之助の声は拙者の身体を、石とさせてしまう。
この時も、拙者は左之助の声に動きを止められてしまい、唖然として見上げてしまったのでござる。
どうして・・・抗えないのか。
左之助は、再びあの笑顔を見せると、自らの右手をそっと、重ねてきた。
この冷えかけていた手を、拙者よりも大きな手のひらが包み込んできた。
その温もりたるは・・・
「こうすりゃ、あったかいだろ」
照れもなく言い放つ、左之助が。
瞬間的に眩く見えたのは果たして、目の錯覚でござったか・・・
「あ・・・あぁ・・・かたじけない」
それだけを言うことが、やっとで。
おまけにどういうわけか、左之助から視線が離れなくなってしまった。
・・・拙者の視線に気づいているのか、否か。
左之助はふと、視線の方向を変えた。
「何だよ、肩も濡れてるじゃねぇか」
「え?」
彼の言葉に誘導されるように、拙者は右肩を見てみた。
頭上にある枝の、葉より滴り落ちてくる雫が先ほどから、拙者の右肩を濡らしていたのでござる。
所詮は雨宿り、しかもどこぞの軒下というわけではござらぬから当然、雨粒一つから逃れられるわけがない。
「身体が冷えちまわぁ。こっち、来ねぇ」
左之助は半纏を片肌、脱いだ。
素肌をさらした右腕が、拙者の右肩を掴んで・・・
「左、左之っ」
・・・思わず狼狽えてしまったのは、拙者の身体が左之助の、右脇腹へぴったり、寄り添っていたから。
炎のような肌の熱さが、わずかに拙者の思考を奪った。
「これで、濡れねぇだろ」
ニヤリと笑いながら、左之助は片肌脱いだ半纏をさらに、拙者の頭上からかぶせた。
「・・・あ・・・」
「そんな顔する前に一言、礼を言えばすむだろ? 剣心」
いったい、どんな顔をしているというのだろう。
鏡があるわけではないから、よくわからない。
気にはなったが、やはり左之助の言うとおり、礼を言うのが一番のような気がした。
「あ、ありがとうでござる、左之」
「おぅ」
・・・雨音。
回りには、雨音しかなかった。
葉を打つ音。
滴る音。
土を跳ねる音・・・
無数に満ちあふれる、雨の音。
目を閉じれば、
様々な物音の中に「雨」が居る。
「人」ではなく、「雨」が居る・・・
・・・「雨」と・・・
自分、そして「この男」だけ・・・
そう・・・たった、それだけのことでござった。
雨が、降り続いている。
その雨を、忌み嫌っていた。
否が応にも思い起こさせる忌むべき記憶を、拒絶していた。
なのに・・・どうして・・・
胸の中に、居るのは。
「ずっと、このまま続いてくれれば・・・」
と、切に願う拙者の想い。
拙者の願い。
あれほど嫌っていた雨だというのに、今更そう願うことはわがままだろうか。
いや・・・わがままだと、思われてもいい。
思われてもいいから・・・
この「時」を、得ていたい・・・
「左之助・・・」
右肩を捉えて離さない、左之助の右手。
必然、拙者は左之助へと身体を寄せる・・・
薄く、汗ばんだ肌。
熱く、脈動していて・・・
息が詰まるほどに、それは・・・
・・・拙者は・・・不覚にも左之助の、肌の香りに立ち眩みを覚えた・・・
「左、之・・・」
・・・思わず、
左之助の腋下へと、拙者は・・・口づけてしまった。
「剣心・・・」
驚いたように、左之助の視線が拙者を射る。
拙者は、気恥ずかしくなってそのまま、俯いてしまった。
「・・・誘うなよ・・・これでも我慢、してんだぜ」
「左、左之・・・っ」
自身でもわかるほど、顔が火照り上がる。
・・・何ということを、してしまったのでござろうか・・・
羞恥で拙者、穴があったら入りたかったでござる。
「・・・なぁ・・・剣心」
「ん・・・?」
「・・・雨、止んだら・・・長屋、来るか・・・?」
「え・・・」
驚きに顔を上げた瞬間、
左之助の唇が、羽のように降ってきた。
拙者は目を閉じた。
舞い降りて来るであろう、彼の唇を・・・
・・・時には・・・
このような雨宿りも、良いかも知れぬ・・・
[ 赤毛の優男 長身の男 ]