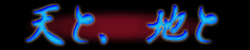
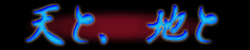
それぞれの耳に響いてくるものは、
人々の取り留めのない会話や喧噪・・・雑踏の嵐。
だがどこを切り取っても、それは「新年」に関する事柄ばかり。「おめでとう」だの、「今年もよろしく」だの、ありきたりな台詞で占めている。
が、それらがどれほど耳を穿とうとも、当の本人達はそれどころではない。
「おいっ! 絶対に手を離すんじゃねぇぞっ。しっかりくっついてっかァ?」
やや間抜けな声を発し、背後を顧みたのは。額の紅はちまきも鮮やかな、長身痩躯の相楽左之助。この寒空でありながら、半纏一枚に素肌へ晒しを巻いただけの軽装。かつその半纏、背には大きく「惡」と記されているのだから、奇妙なことこの上ない。
「あぁ、オレは大丈夫だっ」
そのすぐ足下から声を発したのは明神弥彦。左之助の腰辺りまでしかない背丈をグイッとのばし、人混みに紛れぬように声を荒げる。
「薫っ! 大丈夫かよッ? オレの手ェ、離しそうだぜっ」
「大丈夫!」
負けじと声を張り上げたのは神谷薫。晴天の空と見紛うばかりの振り袖に身を包み、頭には同色のリボンを結んでいる。隙間もないほどの人混みでなくば、目を引くほどの艶やかな姿なのだが、今はそれどころではない。薫は改めてしっかりと弥彦の手を握りなおし、背後を顧みた。
「剣心ッ? ちゃんとくっついているわよねッ?」
「あぁ、これ、この通り」
名を呼ばれた男は、薫の手を強く握りなおす。
「大丈夫でござるから、左之、先陣は任せたでござるッ」
ともすれば、薫に隠れてしまいそうになる身体を精一杯背伸びして、彼は左之助に存在を明らかにした。
最も彼は・・・緋村剣心は、その特徴的な赤い髪のため、たとえ短身痩躯であっても目をひきつけずにはいられない。おまけにこの時代、帯刀しているのだから目立たぬはずがない。
が、それぞれがどんなに派手な・・・異様な出で立ちをしていようとも、この人々がひしめき合う状況ではすべてが霞み、無駄というものである。
左之助、とりあえず出欠を確認すると、
「よしっ! このまま一気に抜けるからなっ。しっかり、付いてくるんだぜェ!」
彼の一言に、三人は重々しく頷いた。
・・・日付は元旦。
身も心も何もかも洗われるかのような思いに捕らわれる、新年の到来。
元旦は寝正月と相場は決まっているが、無論、初詣に行く人々は決して少なくはない。
神谷薫もまたその一人で、女の細腕でありながらも一つの流派を継承している者として・・・即ち家長として、元旦に詣でることを望んでいた。
が、たとえ家長と言えども女たる身。もっぱら元旦ともなれば海のうねりのように人が溢れ返る。
それがわかっていて、みすみす一人で行かせることなど緋村剣心にはできようはずもなく。
何より、その行動を同じ屋根の下に住まう弥彦が見逃すはずもなく、まして毎日のように訪れる左之助がくっついて来ぬ訳がなく・・・
結局、四人での初詣と相成った。
ところがやはり元旦での初詣、人の数は想像を遙かに越えていたと言ってもいい。
四人で賑やかに来たのはいいが、この様子では必ずはぐれてしまうだろう。
そこで剣心、一計を案じた。
四人の中で一等、上背があり、とりわけ行動力も並々ならぬ左之助を先頭に立て、続いて弥彦、薫と位置づけて殿を自分が務め、互いに手を繋いで行こうというものだった。
左之助や弥彦からは、まるで遠足のようだと、幼子のようだと不満を漏らしたが剣心、そこはうまく言葉を並べ立てて二人を納得させた。
薫はと言えば、やや頬を赤らめて顔を伏せている。一言も発しなかったから、異存はないのだろう。
畢竟、
剣心の案は功を奏し、四人が同時に柏手を打つことができ、四人が同時に帰還することができたのである。
「ふい〜・・・。すっごい人混みだったなぁ!」
ようやく人々がまばらになってきた頃、左之助は弥彦の手を離してつるり、顔を撫でた。凍てつく空気に白い息、だがその頬、微々たる汗が滲んでいる。
「あ〜・・・オレなんか、つぶされるかと思った・・・」
薫から手を離し、弥彦は両手を広げて大きく、深呼吸。四人の中で一番背丈の低い彼は、見るものと言えば他人の懐やら帯ばかりで、それがどんどん迫ってきていたのである、新鮮な空気を求めてしまうことは当然といえる。
「本当、ものすごい人だったわねぇ! 良かったぁ、みんながいてくれて」
薫もまた、剣心からするりと手を離すとふうっと息を吐いた。ついつい振り袖を見遣り、ほころびや汚れがないかどうか確認するあたり、やはり乙女である。
「何とか切り抜けたでござるなぁ・・・良かった、良かった」
満面の笑みを浮かべ、三人の顔をそれぞれ見遣りながら、剣心は心底ホッとしたようにそう言った。彼もまた人混みに埋もれて着物のあちこち、解れてしまったりしている。
「オレはもう二度とゴメンだぜ。あんな人混み、たまンねぇよ」
背中にくくりつけてある竹刀、存在を確認しながら弥彦はぼやいた。竹刀よりも、乱れてしまった髪型を何とかしろと薫、口を開きかけたがついと手が、まず伸びた。
「仕方がないでしょ? 昔から家長が初詣に行くことになっているんだから。父さんがいない今、私しかいないじゃない」
弥彦の髪の毛に指を絡ませながら、やや押さえつけるように直す仕草は、母親であると言うよりはまるで姉。弥彦、顔を赤らめながらそんな薫を突っぱねようとする。
「何してんだよ、薫! ンなことしなくていいってッ」
「もう、うるさいわねッ。そんなことじゃ、燕ちゃんに嫌われちゃうわよっ」
「なっ、何でそこで燕の名が出てくるんだよっ」
たちまちの如く顔面が赤らんだものだから、左之助、グイッと彼に腕を絡ませ引き寄せた。
「おっ、何でェ? やけに顔が赤いじゃねぇか。さてはおめぇ、燕ちゃんのこと・・・」
「そっ、そんなんじゃねぇよッ! 何を、馬鹿なこと・・・」
狼狽も甚だしい、まさに初な反応に左之助、ますます悪戯心を沸き立たせる。
「そうか? おめぇ、何だかんだって素直だからなぁ。すぐに顔に出るの、知ってたか?」
「なっ・・・! そ、そんなこと・・・っ」
「おめぇ、何をお願いしてきたんでェ。燕ちゃんとの仲が進みますように、てか?」
「違ェよ!」
ブンッと左之助の腕、弥彦は力の限り振り払った。クルリと彼に向き直り、両手に腰を当てて左之助をギラリ、睨め付ける。
「オレぁな! 一日も早く、一刻も早く、日本一の剣士になりてぇんだ! 願うことと言ったら、それっきゃねぇだろがッ」
「日本一・・・ね。そうか、弥彦らしいじゃねぇか。まぁ、せいぜい頑張るこった」
「あ、てめェ! 今、オレのこと馬鹿にしやがったなッ? もう許せねぇッ」
弥彦、鼻息荒く背中の竹刀へ手をかけた。
「お? いいぜ、俺は。いつでも受けて立つぜぇ」
左之助、楽しそうに弥彦を見た。が、拳を構えることなく、下袴へ両手を突っ込んだままのその態度がますます、弥彦には面白くない。
「この・・・っ」
「あー、もう! いい加減にしなさいッ、弥彦、左之助!」
とうとう、薫が鋭い声を投げた。
途端、二人の動きがピタリと止まる。
「新年早々、何をやっているのよ。『笑う角に福来たる』って、知らないの? 弥彦、些細なことで目くじらを立てないっ。左之助! あんたもからかうの、大概にしておきなさいよっ」
・・・天下の往来で、小言を食らってしまうとは・・・
左之助、
「・・・へいへい」
と言いながら小さく舌打ち。
弥彦、
「あぁ・・・わかったよっ」
と言いながらぷいっとそっぽを向いてしまった。
「あぁ、もう・・・あんた達は・・・」
薫、深々と思わずため息。
ここぞという時には団結力が・・・互いに深い信頼関係で結ばれているというのに、普段はそんな様子を微塵も見せない。むしろ肝心な時に見せる、不思議なほどの意気投合したやり取りの方が不可解に見えてしまうのだから、薫には彼等の心根がいまいち、理解できない。
理解できないがそれでも、そんな彼等を信じている自分もまた、不可解であると薫、何気なく思った。
「そうか・・・弥彦は日本一を目指すのでござるか。頑張るでござるよ」
それまで静観していた剣心が、落ち着いた口調で弥彦に言った。
顔を上げた弥彦が見たのは、剣心の柔らかな微笑。
たったそれだけなのに・・・弥彦の心、すぐさま晴れ渡るのだから単純といえば、単純。でも・・・純真といえば、純真。
「それで? 左之助は何を願ったのでござるか」
緩やかに、何気なく剣心は話題を変えた。・・・願わくば、二人の口論をいつまでも聞いていたいような気もしていた。確かに新年早々、口論をするのはどうかとも思うのだが、そうした普段通りの空気が、剣心にとっては心地よい。
「俺か? 俺は・・・まぁ、他の誰よりも、強くなれるように、かな」
「ハハ、それは左之助らしいでござるな」
歩み出しながら、剣心は答える。
「他の誰よりも・・・って、日本一になるってことじゃ、ねぇのか?」
弥彦は両腕を組み、左之助を見上げて言った。齢、未だ十であるというのにこの少年、時折大人びた仕草を垣間見せる。
「いや・・・違ェよ。どっちかってェと・・・世界中の誰よりも、てとこかなぁ」
「左之助・・・」
弥彦の目が、点になった。
それは驚き、というよりはむしろ、自分よりも広大な視野の中で、さらなる高みを見据えている左之助への畏敬の念だった。
顔を合わせば口論の絶えぬ弥彦だが、その心根では剣心と対等で・・・相棒であり、仲間であろうとする彼の背中に畏敬を抱いている。
「ハハ、だがまぁ、結局は俺が足掻かなけりゃ、強さなんざ身に付かねぇのよ。もともと、神さんに頼る俺じゃねぇからよ」
大口を開けて高らかに笑い飛ばして左之助、今度は剣心の肩をポンと叩く。
「それで? おめぇは何を願ったんでぇ」
「拙者か? 拙者はまぁ・・・この逆刃刀がいらぬ時代が、早く訪れますように・・・でござるかな」
「・・・チッ」
グリグリと。左之助は小さく舌打ちするなり剣心の頭を撫でつけた。撫でつけるというよりは、押さえつけるような力加減である。剣心、思わず悲鳴を上げた。
「なっ、何をするでござるか、左之ぉ〜」
「どうしておめぇは、いっつも他人のことばっかりなんでェ。ちったぁ、自分の欲を出してみちゃァどうだい」
「そ、そんなもの拙者・・・」
「あぁ、もう・・・おめぇも相変わらずだなぁ・・・」
「年が改まったからと言って、拙者の中身まで改まるわけではござらんよ」
「そりゃまぁ、そうだが・・・」
やれやれと。左之助はため息を付きながら頬を掻く。
どうもこいつは、自分のことよりも他人のことを・・・周りのことを優先しやがる。だからまぁ・・・放っておけねぇところ、あンだよなぁ・・・
「ところで薫は? 薫は何を願ったんだよ」
と、沈黙を守り続けている薫に弥彦は言葉を投げた。
薫、一瞬瞳を巡らせ言葉を選んでいるのか、唇、曖昧に開いた。
「そ、そりゃ決まっているじゃない。神谷活心流に、一人でも多くの門下生が増えること! そして神谷にいるみんなが健康で、元気でいられますようにって」
「ふーん・・・」
それきり、薫は唇を閉ざしてしまった。
そんな彼女を見て弥彦、何かしら感じるものがあった。が、口出しするような、あるいはかけるべき言葉を見つけられるほど、彼はまだ大人になってはいなかった。
だが感づいたのは何も、弥彦だけではない。左之助もまたすぐに、察知してしまう。
「・・・嬢ちゃん」
スッと彼女の側へと身を寄せて左之助、軽く肩を叩いた。
「ま・・・頑張りな」
「・・・左之助・・・」
薫がゆっくりと、面差しを上げた。
大きな二つの瞳が、左之助の瞳に染み込んでくる。
「うん・・・ありがと」
にっこりと、輝くばかりの満面の笑みに、左之助はニッと笑って応えた。
・・・それぞれの会話を、剣心は先だって歩きつつ、背中でしっかりと聞いていた・・・
若水で沸かした茶を飲みながら、神谷家ではおせち料理に舌鼓を打っていた。
刻限は昼九ツ。
皆は夢中で箸を伸ばしている。
「あ、左之助! オレが食おうと思っていた栗きんとん・・・」
「へへーんだ。早い者勝ちだぜィ」
ひょいっと摘むなり、口の中へと金色の粒は放り込まれてしまう。
「ああぁ〜ッ」
弥彦、絶望の声を上げた。
「おぉ〜、こいつはうめぇ。剣心が作ったのかァ?」
早々に箸を置き、茶を味わいつつ既にくつろいでいる剣心へ、左之助は嬉しそうに尋ねる。
「あぁ、それは拙者が作ったでござるよ」
「それじゃ、こっちの黒豆は、と・・・」
左之助、黒豆に箸を伸ばして頬張るなり、画然に表情、硬直した。
まさか、と恐る恐る傍らへと視線、移してみれば・・・
胸を弾ませながら見守っている者が約、一名。
薫である。
「どうかしら、左之助ッ? その黒豆、私が煮付けたの!」
「・・・嬢ちゃんが・・・?」
「えぇ! どうッ?」
「・・・・・・まずぃ」
途端、
「何ですってェ〜ッ?」
有無を言わさず、拳が飛んできたことは言うまでもない。
「あぁ、薫殿! 新年早々、そんなに怒っては・・・」
剣心、制するのが遅すぎる。
既に拳は左之助の頬へものの見事、命中していた。
「あっ、あぁ! そ、そうよね、アハハハ・・・ごめん、左之助・・・」
「・・・遅ぇよ、嬢ちゃん」
ヒクヒクと、口の端を痙攣させながら笑う左之助。
でも・・・
「まぁ、いつものこった! そうでなくちゃ、嬢ちゃんじゃねェやな。さぁて、俺ァそろそろ帰るとすっか」
「え?」
その時、誰もが驚いた面差しで、立ち上がった左之助を見遣った。
左之助、意外そうな表情で彼等を見遣る。
「何だ・・・どうした?」
「いや・・・お前がこんな、昼間っから帰るなんて、思わなかったからよ」
弥彦の言葉に、
「そうよ。私てっきり、今日は泊まっていくものとばかり・・・」
薫が続けば、
「お主のことだ、ここで寝正月を決め込んでいるのだと・・・。長屋は寒いでござろう?」
剣心、狐に包まれたような面差しでそう言った。
「あ、あぁ・・・俺も、本当はそうしようかと思ってはいたんだがな。すまねぇ、修達との約束が入っちまってなぁ。あいつらと新年会をすることになってンだよ」
まさか自分がこれほど歓迎・・・いやいや、屋敷にいることが当然という顔ぶりで言われるとは思っていなかった左之助。思わぬ展開に狼狽こそすれ、嬉しくないはずがない。
不器用な手つきで頭を掻く仕草に、剣心はふっと、頬をゆるめた。
「そうか、それは仕方ござらぬなぁ・・・ちょうどお茶が切れたところでござるし、立つついでに左之を見送るとしようか」
剣心は急須を手にすると、すっくり立ち上がった。
「何でェ、俺ァ、ついでかよ」
「まぁ、そうぼやくな」
クスクスと、剣心は小さく笑った。
「じゃあ、また明日来っからよ。その時はよろしく頼まぁ」
薫と弥彦に別れを告げ、左之助は部屋を出た。
・・・背中を、剣心が付いていく。
ミシ、ミシ。
床が小さな声を染み出して、二人の重みを訴える。
だが、彼等の声が聞こえても、二人自身の声は聞こえてこない。
互いに無言であった。
けれど、苦痛の伴う無言ではない。
別段、話す事柄もなければ尋ねる事柄もない。
何もないのであれば、言葉を交わす必要など皆無である。
剣心はとりあえず、急須を厨へ置いてくると、左之助とともに正門玄関へと向かった。
左之助は土間へ降りた。
「・・・悪いな、剣心。本当はもっと、ここに居ようかと思ったンだが・・・」
「いや、構わぬよ。仲間や友人との約束は、何よりも大事でござるから」
「剣心・・・」
微笑みの中に、一抹の侘びしさが宿る。
誰にでも向けられる笑みではない。
世間体のための笑みではない。
それは、左之助だけに見せる・・・心の微笑。
静寂が、わずかに満ちる。
「明日・・・また、来るよ。そうだな、夕刻に・・・」
「夕刻でござるか・・・。わかった、皆にもそう、伝えておこう」
「俺は、おめぇだけ知ってくれりゃ、それでいい」
「左之・・・」
ドクリ、と。
剣心の胸の中で何かが弾む。
だが、それらを垣間見せようともしない。
やはり、微笑を浮かべたまま左之助を見つめている。
「そうもいかぬよ。この屋敷の主は・・・薫殿でござるから・・・」
「・・・あぁ・・・そうだな・・・」
しばらく、左之助は剣心の微笑を穴が空くまで見つめていた。
剣心もまた、左之助の眼差しを真正面から見つめて・・・
・・・やがて、
「じゃぁ・・・俺、行くわ。また明日な、剣心」
「あぁ」
踵を返し、半纏の裾、翻り。
「惡」一文字とともに、紅のはちまきが空を舞う。
空を、舞って・・・
・・・舞い・・・
「左之っ」
不意に唇からこぼれたのは男の名。
左之助、何事かと再び背後を振り返る。
剣心が・・・
袴の両脇できつく、拳を握りしめていた。
既に、微笑はない。
「あっ、明日は・・・拙者が、お主の所に・・・長屋へ、行く」
「!」
彼の台詞に、左之助の表情が強張った。
それでも剣心、とつとつと。
「いつも・・・お主ばかりが、ここへ来るのでは・・・割に合わぬ、だろう? だから・・・明日は、拙者が・・・」
彼が何を意図として話しているのか、左之助には明瞭に理解できていた。
だから、思わず剣心の元へと歩み寄った。
駆け寄りたいはずなのに、駆け出してあの小柄な身体を抱きすくめようと思うのに、今日ばかりは左之助の身体、思うように動いてはくれない。
・・・寒さの・・・ためなのか・・・? それとも・・・
「剣心・・・」
「明日は拙者が、お主の長屋へ・・・」
「駄目だ」
「・・・なぜ・・・」
「駄目なものは、駄目だ」
「左之・・・」
己が目の前、剣心の表情が薄曇りに染まっていく。左之助は、そんな彼の心中を察して激しく首を振り、否を唱える。
「俺の長屋は、水瓶の水が凍るぐれェ寒いところだ。そんなところに、おめぇが来るこたぁねぇ」
「しかし・・・」
「あんな極寒のところに、おめぇを招き入れたくはねぇんだよ。俺ァ・・・おめぇを、凍えさせたくはねぇ」
「左之・・・」
剣心にとっては、精一杯の告白だった。
左之助の長屋へ行く、と告げることは心の一部を暴露してしまう・・・殺してしまうかのような激しい痛みを伴った。
それでも、今の剣心は・・・
「左之助、拙者はっ、」
「言うな、それ以上ッ」
やや口調を強め、左之助は言い放った。
剣心、キュッと唇を閉ざし・・・
左之助の面差し、ありありと苦渋が滲む。
「俺だって・・・俺だって、おめぇと同じ思いさ。けどよ、今日だけはなんねぇ。わかってンだろ・・・?」
「あぁ・・・」
「だったら・・・そんな顔、すんな」
「え・・・?」
剣心には、自分がどのような表情をしているかなど、皆目見当も付かなかった。いや、普段から鏡を見る習慣などあまりないのだから、想像すらできないのが本音だが。
それでも、彼には自分自身の心中すら、計りかねている部分がある。
が、左之助はそれらを綺麗に見破っていた。
「左之・・・?」
「・・・たまらねぇ顔、すんな。我慢、できなくなっちまう」
「!」
全身が、落雷にあったかのように硬直した。瞳が見開き、唇がわななく。
左之助は・・・小さく不敵に笑んだ。
「俺ァ・・・迷信を信じる質じゃねぇ。けどよ・・・おめぇが相手だと、何もかも、信じたくなっちまうんだよ・・・」
「左之・・・」
「それに・・・おめぇが自分の歳、気にしてンの知ってたらなおさらによ・・・」
剣心が・・・左之助が、互いに互いを求めていることなどは当の昔に知れていた。
できることなら、今すぐにでもこの場に押し倒して、臙脂色の単衣に潜む肌を貪り尽くしてやりたい。
そんな一種、狂気を帯びた衝動を左之助は、辛うじて抑え続けていた。
どれほど、剣心が潤みを帯びた眼差しで投げかけてこようとも・・・
今日だけは、駄目だ。
左之助、苦虫をつぶしたように奥歯を噛みしめ、言葉を搾った。
「元旦だけは、なんねぇ・・・元旦だけは。いくらおめぇが欲しくっても・・・駄目だ・・・。そうでなきゃ、何のために俺が修達との約束を作ったか、わかりゃしねェ・・・。わかってくれるよな、剣心・・・?」
「・・・あぁ・・・わかる・・・わかっているよ、左之・・・」
ゴクリと喉を鳴らしながら、剣心はか細く応えた。
「剣心・・・」
左之助の、唇が・・・
「左之・・・」
近づいてくる気配に、剣心の胸は早鐘を打ち始める。
眩暈を起こすほどの、激しい動悸。
・・・と・・・
触れあうはずの唇が、スルリと滑り抜けた。
あっと剣心、いつの間にか閉じていた目を見開けば、
「明日は・・・覚悟しとけよ」
熱っぽく、されど冷然と・・・。胸底を抉るような声音が耳朶へと吹きかけられた。
鬢に彼の吐息を覚え、剣心、クラリと立ち眩むのを必至に、堪えた。
「左・・・っ」
左之助は無言のまま、剣心から離れていく。
そして、表情を見せぬままに足早に立ち去り・・・
・・・剣心は。
自らの肌に一寸たりとて触れてくれなかったそのもどかしさに、火照り上がってしまった己が肉体を持て余した。
吹き込んでくる北風が、
一人取り残された剣心の肌を掠めていった。