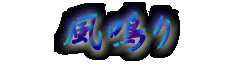
[ 1 2 ]
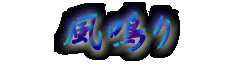
ビョオォォ・・・
吠えるような、叫ぶような。
凄まじい音がこだまする。
じっと耳を澄ませるも、聞こえるものはそればかり。
・・・否、時折、
バラバラバラっ
屋根を穿つ無数の音が。
・・・雨粒。
束のようになって襲うこともあれば、まばらになって落ちてくる。
ビオォォ・・・
ザザっ・・・バララっ
無数の音の合唱に、長身の男は半ば、苛ついたように毒を吐く。
「チッ・・・凄い風鳴りだぜ・・・」
頭を軽く掻きむしり、彼は耳朶の集中力を切った。
指に梳いた漆黒の髪、しとやかに濡れて肌へと絡む。
瞳、上げれば今にも崩れそうな屋根がある。
太く、どっしりとした梁。奥深い闇色に染まりその空間のみ、異なるものであるかの如く。不気味さを感じずにはいられぬが、これらがなくば恐らく、この風でたちどころに飛ばされていただろう。
今は、見かけに寄らずしっかりしているこの小屋が、男にとっては心の頼り。
何しろ、予期せぬ嵐に遭遇したのは何も、自分ばかりではないのだ。
濡れた衣装を、転がっていた角材に引っかけて吊しているが、一刻ほど経つというのに未だ、雫を滴らせている。握力や膂力には自信があった、しっかり搾ったはずなのに・・・。男、がっくりとうなだれた。
うなだれてチラリと眼差し、上向けば。
「惡」一文字を記した半纏と下袴とともに、並ぶは襦袢に袴、緋色の単衣。
パチッ
不意に、薪の爆ぜる音に男、我に返る。
小屋の中央、土の上。寄せ集めの焚き物にて火をおこしていた。
時は真夏、されどどういうわけだか肌寒い。
おまけに・・・
「う・・・」
焚き火の向こう側、もぞりと寝返りを打つ者が。
動きに合わせて散らばる藁・・・男、それを見てうっそりと立ち上がった。
一糸纏わぬ姿が、炎の灯りに浮かび上がる。
黒い影が筋骨を刻み・・・
拭いきれていない雨粒、浅黒い肌を伝っててらてら光り・・・
爪先、静かに歩み寄る。
小屋の壁際に盛られた藁の束。何のためにあるのかよくわからぬ。
内部を見渡しても、鎌だの縄だの様々な道具があれど、どれもこれも皆、赤茶けた粉を噴いている。
が、男にはこの小屋が、いかなる理由で存在していようとも全く、意に留めることはない。
ただ、思うことがあるとすれば「感謝」のみ。嵐の中、突如として現れた「雨宿りの場所」に、男はひたすら感謝する。
それ、だけだった。
藁の、山の中に。
もう一人の客人がいる。
埋まるように、身体を横たえているのは見たこともない赤毛の、優男。左頬に大きな十字傷が、一瞬視線を引きつける。
男は、誇る上背をやや屈め、散らばった藁を集めて再び、優男へとかける。
・・・優男は顔面蒼白、微かな呼吸のみにてそこにいた。
つと、額に手をやれば・・・
「熱いな・・・」
チッ。小さく舌打ちして男、苦虫を潰したように顔をしかめる。
偏に、この嵐が憎らしい。
嵐が来なければ、今頃自分達は葵屋に帰って夕飯をつついていただろう。
こんな、見も知らぬ竹林の、しかも古びた、いつ壊れるとも知れぬ小屋の中に甘んじていようとは・・・
「畜生。剣心を引っぱり出してくるんじゃなかったぜ」
今更ながらに、己が愚行を罵る。
京都の地に来たのは、いつだったか。確か、初夏の頃合いではなかったかと思う。
この優男を追いかけて、自分は京都までやってきた。
ようやく顔を合わせられたかと思えば、想像以上の激戦が自分達を取り巻いた。
それはこの、長身を砕かれるかと思えるほどの、否、それ以上の猛襲が、優男に襲いかかっていた。
小さな身体のどこで、そんなものを受け止めてきたのか・・・
男には不思議でならず、かつ、今にも壊れてしまいそうで恐ろしくもなる。
だから、なのか。
満身創痍、三途の川を見たかも知れぬ優男が快復した時、男の喜びたるは凄まじいものだった。
さすがだ、という尊敬と畏敬の念・・・同時に、いつも以上に愛しい想いが溢れてきた。
気づけば。
優男を連れ立って京都見物に出ていた。
久しぶりに優男と肩を並べて歩いた、東京ではなく、京ではあったが。
だが、すべてのしがらみを忘れてしまえるほどに男は、嬉しくて嬉しくて、たまらなかった。なのに・・・
西へ東へ、北へ南へ、あちらこちらへと彷徨していくうちに何と、二人は竹林の中で迷ってしまった。
迷ってしまっただけならばまだよい、突然、空模様が妖しくなったかと思えば凄まじいばかりの雨と風。
二人は濡れ鼠になって疾駆したのだが、竹林を抜けることが出来ず、気づけばこの小屋にたどり着いていた。
幸運、と言うべきだろう。
言うべきなのに・・・
「すまねぇ、剣心・・・無理、させちまったな・・・」
藁の山へ腰を下ろし、男はそっと、十字傷へ指を這わせた。
小屋へ飛び込んだとき、既に優男は意識朦朧としていた。
いつからこのような状態だったのか。気づかなかった自分自身に腹を立てながらも、男は手早く彼の衣装を脱がせていった。雨粒を拭うこともままならず、男はなるべく、肌を見ないようにして優男を藁の中へと埋め込んだ。
そして、手早く火をおこしてから、自分もまた衣装を脱いだのだった。
「きっと、背中の傷がまだ、充分に癒えてなかったんだ・・・こんなことになるなんて・・・」
凛々しい眉が、弱々しく。眉間にしわを刻んで、唇を噛んで。
拳を握りしめた。
「う・・・あ、あぁ・・・」
・・・と。
薄く、小さな呻き声。
何事かと男、優男を顧みる。
彼は唇を真っ青に変色させ、柳眉な眉を歪めてしきりに、何かを呟いている。
「剣心、剣心っ? どうした、おいっ。どこか苦しいのか?」
肩を掴み、揺さぶってみるが反応はない。ぐったりと弛緩したまま、瞳を閉じたまま。
藁が離れ、生白い肌が炎に浮かぶ。
「あ・・・俺、は・・・もう・・・」
譫言が。
紡ぎ出す言葉を男、聞き取ろうと必死になって耳朶を寄せる。
彼の唇、耳朶に触れるか触れぬかのその、隙間に。
「俺は、もう・・・振るわな、い・・・殺人の剣など・・・俺、は・・・っ」
「剣心・・・」
・・・昔の夢を見ているのだろうか。自分のことを「拙者」ではなく、「俺」と称している。
男は成す術もなく、彼の額を撫でながら凝視し続けた。
背中で、薪が爆ぜた。
「嫌・・・嫌ぁ・・・っ。あぁ・・・ッ」
不意に、優男の両眼がカッと見開かれて虚空を睨み据えた。
肝を握りつぶされたかのように意識が澄み、男は息を呑んだ。
優男の視線は天井へ突き刺さっている。
瞬きもせず、キッと瞳を剥いて。
「剣・・・心・・・?」
おそる、おそる・・・声をかけてみる。
「あっ、ああぁ・・・」
画然、人形の面のような面差し、キュッと萎んで皺を刻み、
「ああぁ・・・、あぁッ」
言葉にならぬ声を発し、右手、藁の下から垂直に突き出た。
「剣心っ、どうしたッ?」
ただならぬ様子に男、思わず優男の右手を握りしめる。
しかし視線はそのまま、全く男の方など見向きもしない。
たまらず、彼は藁の中に身を飛び込ませるなり優男の肢体、力一杯抱きすくめた。
優男は、声を放ち続けている。
風の音を、掻き消すほどに。
「剣心、剣心ッ! 俺だ、左之助だ! わからねぇのか? おい!」
優男は答えない。しきりに何かを訴えるように声を放ち、右手を・・・ついには左手をも天へ突き出して何かを得ようとしているのか、掴み続けている。
捉えるものは、空ばかり。
「畜生っ、何だってぇんだ・・・! 俺ァ、どうすることも、どうしてやることもできねぇのかよッ! 剣心、剣心よォ・・・ッ!」
何が、彼に起きているのか全くわからなかった。
何が、彼で暴走しているのか、全くわからなかった。
何が、彼を苛ませているのか全く・・・わからなかった。
あまりに、理不尽だ。
あまりに、無力だ。
あまりに・・・あまりに、
情けないッ!
「何もわかっちゃいねぇ・・・俺は、おめぇのこと何にもわかっちゃいねぇ! わかったつもりでいた・・・わかっていたはずだったんだ! なのに・・・おめぇが何を悩んでもがいてンのか、さっぱりわからねぇなんて・・・俺ァ、大馬鹿野郎だ・・・ッ!」
熱に浮かされ、過去の忌まわしい何かを思い出し、苦しんでいることは察知できた。
察知できていながら、どうすることもできない自分が不甲斐なかった。
いや、何か出来ると思っていた自分が奢っていただけだ。
たとえ出来たとしても・・・何も知らない、知らなさすぎた・・・!
「畜生っ、剣心・・・!」
思い、あまって。
男は優男の唇を奪い取った。
「む、ぐぅ・・・ッ」
刹那、優男は驚いたように呻いたが・・・やがて、静かに受け入れた。
伸ばしていた両腕をだらりと下げ、男の肩口へと絡め・・・
見開いていた瞳をそっと・・・閉じた。
ようやく訪れたわずかな静寂に・・・
風の音が、混じった。
「・・・剣心・・・」
すっかり静かになった優男を・・・改めて見てみようと唇を離し、面差しを上げた。
藁にまみれて・・・青みがかった両眼が、じっと男を見つめていた。
けれど・・・
・・・なんだ・・・? 視点が、定まって・・・ない・・・?
「剣・・・」
「・・・と・・・」
優男の花びらが、薄く開いた。
男、耳を澄ます。
「・・・と・・・も・・・え・・・」
「!」
艶やかな瞳はゆるく潤み・・・
すぅと・・・落ちた。
「・・・ともえ・・・?」
それは初めて響かせた余韻だった。
ともえ・・・ともえ? ともえって、何だ。ともえって・・・
「女の・・・名・・・じゃねぇか・・・」
絶句、した。
眼下には・・・優男の安らいだ面差しがある。
その面差しは、俺だからではなく・・・
「俺を、『ともえ』だと思ったから・・・か・・・?」
そうかも知れない・・・だが、そうではないかも知れない。
男の胸中を、鼓膜をつんざく風鳴りがこだました。
「何だよ・・・何なんだよ、そりゃぁ・・・俺は・・・俺は、おめぇの心にも引っかかってねぇのかよ? 今、ここにいる俺なんぞより、昔の女を選ぶって・・・?」
思わず、身を包む藁を掴む。
今、こうして握りしめている、手のひらの中にある藁の方がよほど、現実味があった。
実感できた、「握りしめている」、と。
だが、どうだ?
目の前で安堵しきった顔で眠りに落ちているこの男を、
己が腕の中に捉えているというのに何だというのか、この・・・
この、激しい虚無感は・・・ッ!
「剣心・・・剣心っ! おめぇは今・・・今、どこにいるんだよ? おめぇの心はどこにあるんでェ・・・。俺の届かないところか、声が届かねぇところなのかッ? 俺は、俺は結局それだけの男だったッてぇのかよッ」
吠えるような恫喝は、
わずかに・・・風を怯ませた。
男は、唇を噛んだ。
強く、きつく噛みしめた。
ブツっ。
綱が切れるような音、溢れ滴る・・・血。
唇の丸みから、それは雫となって落つ。
ぱた、ぱたた。
「ん・・・」
血は、優男の唇の隙間へ染み込んだ。
何だろうと、無意識に舌先が舐め取る。
知っている、味だった。
嫌というほど味わってきたものだった。
たちどころに、優男の意識は覚醒する。
[ 1 2 ]